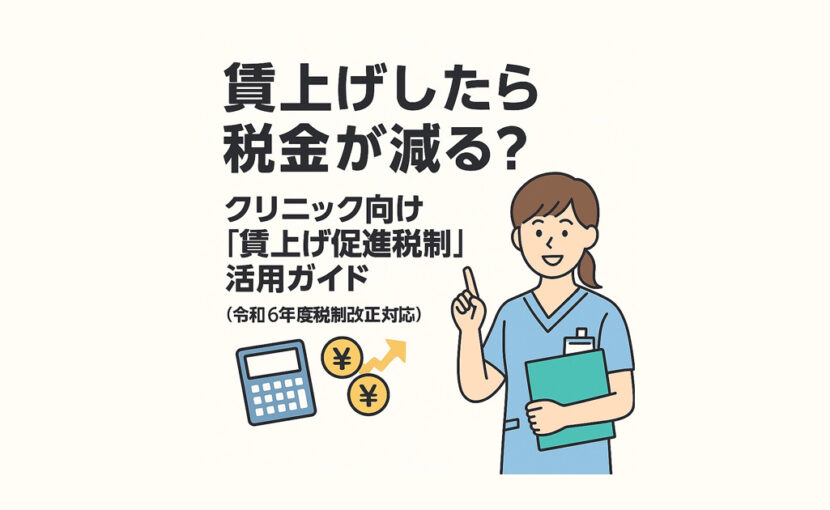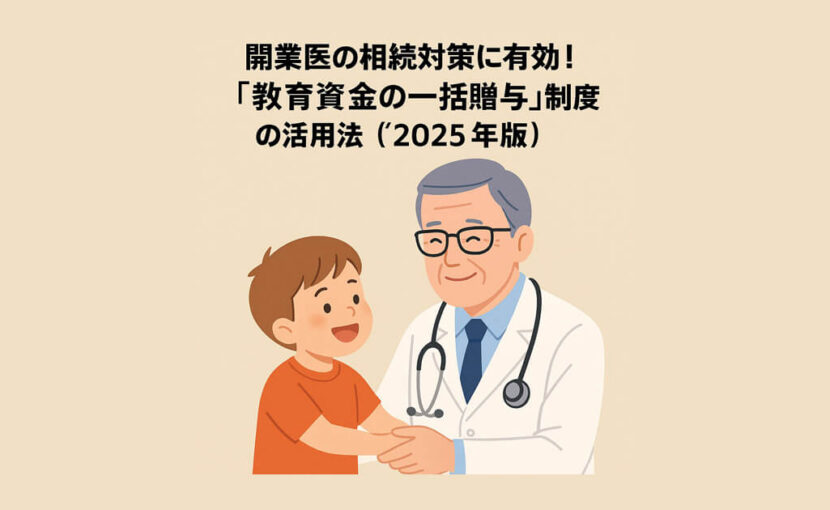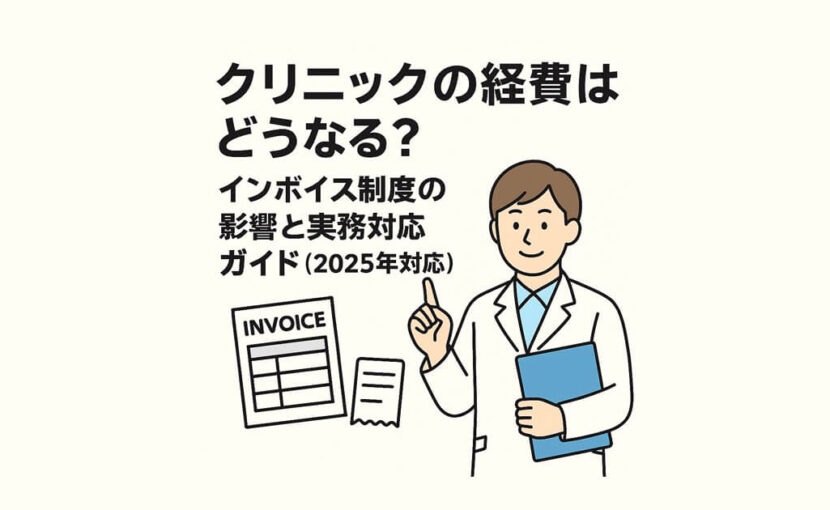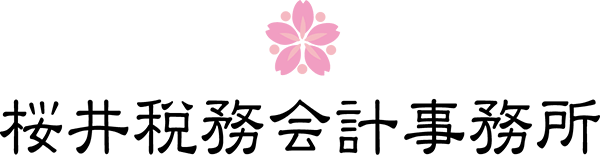税理士の櫻井晃規です。
今回のブログでは「院長先生必見!インボイス制度がクリニックに与える影響と対応策」をテーマに、以下の内容について書いていきたいと思います。
・インボイス制度の概要
・保険診療中心のクリニックは基本的に登録不要
・登録のデメリット
・登録が必要なケース
・院長先生が取るべき対応は?
・まとめ
インボイス制度とは?
2023年10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除を受けるために、一定の記載事項を備えた「適格請求書(インボイス)」の発行と保存が求められる制度です。
インボイスを発行するには、税務署に届出を行い、登録番号を取得する必要があります。そのうえで、取引内容や税率・税額などを記載した請求書等を発行します。
保険診療中心のクリニックは基本的に登録不要
保険診療は消費税の非課税取引のため、インボイス制度の対象外です。
また、自由診療であっても相手が個人の患者様であれば、インボイスの発行義務はありません。
そのため、保険診療を中心に行っているクリニックであれば、インボイス登録は不要なケースが大半です。
インボイス登録によるデメリットとは
インボイスに登録すると、たとえ年間の課税売上が1,000万円以下で本来は免税事業者である場合でも、強制的に課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じます。
そもそも、クリニックが消費税の納税義務を負うのは「2期前の課税売上が1,000万円を超える場合」に限られます。
にもかかわらず、インボイスに登録することで、本来は免除されていた消費税の納税義務が発生してしまう点には注意が必要です。
インボイス登録が必要になるケース
企業向けの健康診断や予防接種の受託は課税取引に該当します。企業側は仕入税額控除を受けるために、インボイスの発行を求めることがあります。
もしクリニック側がインボイス発行に対応していない場合、他の登録済み医療機関に契約を切り替えられるリスクもあります。
特に、課税売上が毎年1,000万円を超えており、企業向け取引が多いクリニックでは、インボイス登録を前向きに検討する必要があります。
院長先生が取るべき対応は?
- まずは自院が免税事業者か課税事業者かを税理士に確認しましょう。
- 免税事業者であれば、原則としてインボイス登録は不要です。
- 課税事業者の場合は、自費診療や企業向け健診などの取引内容を確認し、取引先からインボイスが求められる可能性があるかを把握しましょう。そのうえで、登録しない場合の影響も踏まえ、慎重に判断することが重要です。
まとめ
インボイス制度の影響は、クリニックの診療内容や取引先の性質によって異なります。
保険診療中心のクリニックでは、登録の必要はほとんどありませんが、自費診療や企業向けの取引が多い場合には、インボイス対応が求められる可能性があります。
インボイス登録には消費税の納税義務が伴うため、自院の実情に合わせて正しく判断することが重要です。
当事務所では、医療機関様の状況を丁寧に分析し、制度の仕組みをご説明したうえで、登録の是非について慎重に検討しております。
インボイス制度への対応に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。