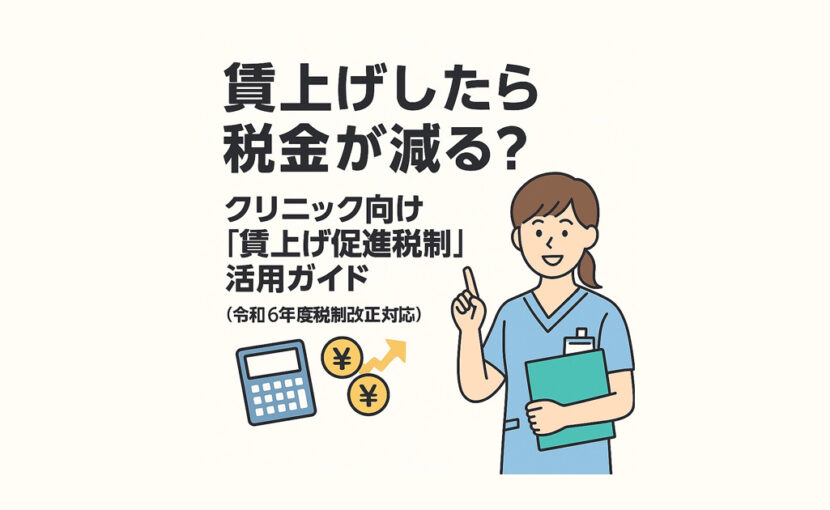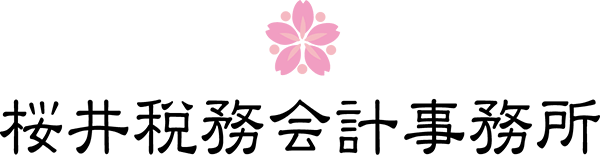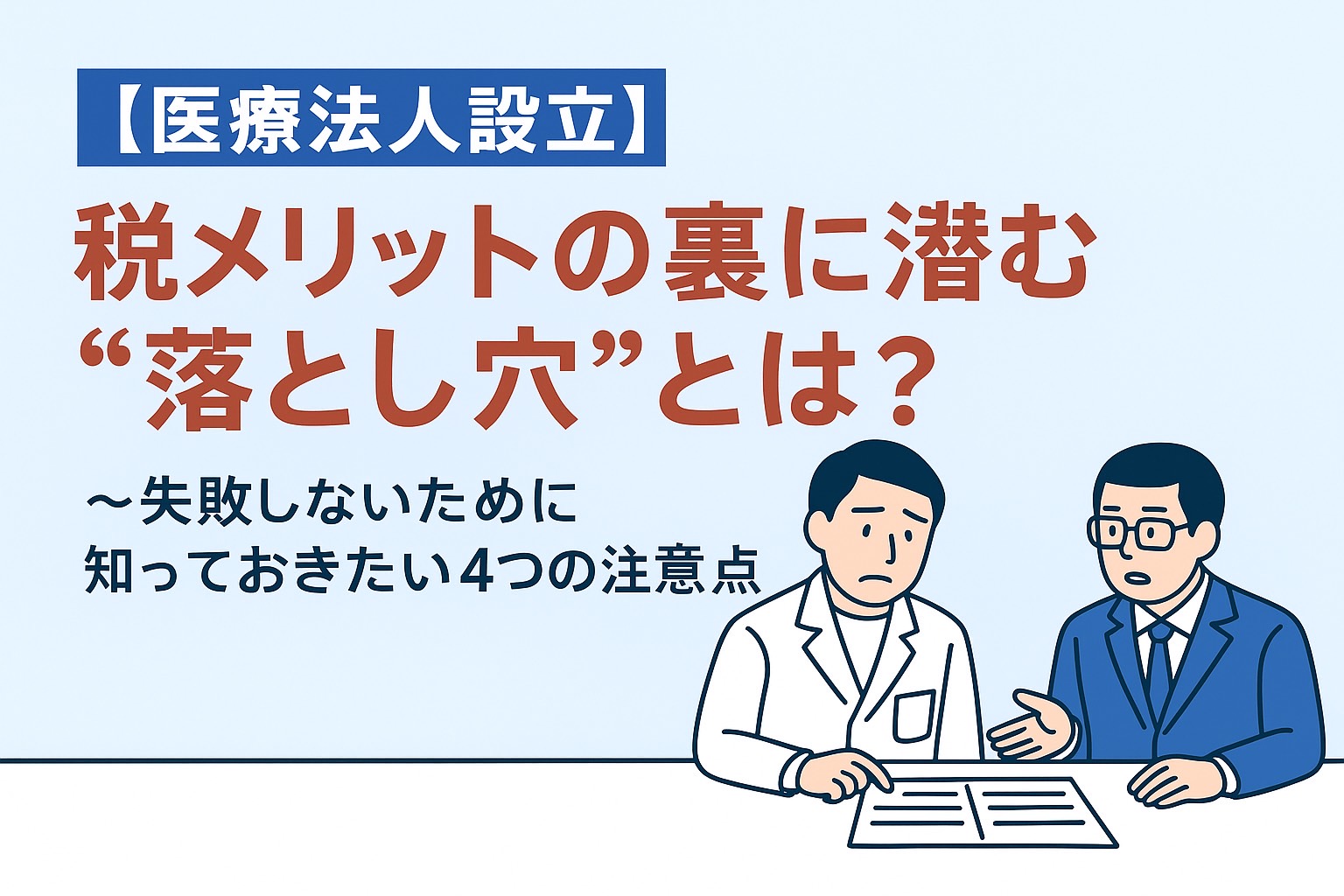
~失敗しないために知っておきたい4つの注意点~ 秋田・青森の医療専門税理士が解説
はじめに ―「節税目的」での法人化にご注意を
こんにちは。税理士の桜井晃規です。
「そろそろ医療法人にした方がいいのか…」
そう悩まれている開業医の先生も多いのではないでしょうか?
確かに、個人事業では所得が増えるほど高くなる所得税・住民税(最高55%)に対して、法人化すると法人税(約30%)+役員報酬に対する所得税という形になり、一定以上の利益があれば“節税効果”が見込めます。
しかし、制度の表面だけを見て安易に法人化を進めてしまうと、
あとで「こんなはずでは…」と後悔するケースも少なくありません。
この記事では、医療法人化を検討する際に知っておくべき4つの注意点を、実務と制度の観点からわかりやすく解説します。
注意点① 社会保険の加入で“思わぬコスト増”に
医療法人にした場合、理事長や常勤理事(役員)は社会保険への加入が強制されます。個人開業時には国民健康保険・国民年金で済んでいたものが、法人化により健康保険・厚生年金の法人負担+個人負担に変化します。
たとえば、理事長の役員報酬を年収2400万円(月額200万円)とした場合、社会保険料は個人と法人あわせて約330万円程度です。国保・国民年金だった個人事業主時代と比較して、200万円程度負担が増える計算となります。
つまり、税率の低さだけを理由に法人化してしまうと、社会保険料の増加分で手取りが思ったほど増えないどころか、逆に損になるケースもあるのです。
☑︎ 実務的には、年間の事業所得(売上から経費を引いた額)が3,000~4,000万円以上ある場合に初めて、法人化による節税メリットを実感できることが多いです。
注意点②「持分なし医療法人」 出口戦略の重要性
現在、新たに設立できる医療法人はすべて「持分なし医療法人」です。
これが意味するのは、法人が解散した場合、残った財産は国や地方公共団体などに帰属するということです。
将来的に、「クリニックで積み上げた財産を家族に残したい」と思った場合、ご家族が医師であれば、理事長を交代してクリニックを承継して頂いた場合には、医療法人の財産に関しても実質的にご家族へ移転することが可能です。
その際、相続税はかからないため、これは「持分なし」の大きなメリットでもあります。
一方で、ご家族などの後継者の方がいらっしゃらず、最終的に法人を解散するというケースもあります。
そこで重要になるのが、法人を“空(から)”にして解散するための出口戦略です。
代表的な方法には以下のようなものがあります:
- 理事長の退職時に合理的な退職金を支給する(役員在任年数 × 月額報酬 × 功績倍率 で計算)
- 退職金の原資確保としての法人契約の保険活用
- 医療機器・内装・設備を定期的に更新して減価償却を進める
これらを計画的に設計しなければ、最終的にお金を引き出せず“もったいない法人”になってしまいます。ご自身の将来を見据えた出口戦略の設計が必要なのです。
注意点③ 借入は“個人のまま”―返済負担が続く
クリニック開業時に、建物の建築費や医療機器購入などで個人名義で借入をしている場合、医療法人を設立してもその借入は医療法人に引き継がれません。
つまり、医療法人化した後は、以下のようなお金の流れの構図になります:
売上(診療報酬)はすべて法人の口座へ → 役員報酬として理事長個人に支給 → そのお金の中から個人借入を返済
役員報酬の中から借入金を返済する必要があるため、理事長個人のキャッシュフローは悪化します。
済のために役員報酬を多く取りすぎてしまうと、今度は所得税・住民税・社会保険料の負担が増え、節税メリットが打ち消されるという本末転倒な事態にもなりかねません。
注意点④ 理事長個人の家計と医療法人に留保するお金のバランス
法人化後に、理事長が個人としてお金を得る方法は主に以下の2つです。
- 役員報酬(法人経費となるが、所得税課税対象)
- 不動産収入(家賃)(理事長がクリニック建物等を所有し、医療法人へ貸付ける場合)
このうち家賃は税務上簡単に変更できないため、生活費をまかなうには役員報酬の設計が極めて重要になります。
ただし、役員報酬を高く設定しすぎると、前述の通り所得税・社会保険料がかさみ、法人化による節税効果が薄まってしまうことも。
また、役員報酬で生活費がまかなえず、法人から“ついでに”個人の支払いをしてしまうと、それは「役員貸付金」という扱いになります。医療法人に返済などを行わない場合は、最悪の場合役員賞与として認定され、所得税が発生するリスクもあります。
この役員貸付金には:
- 法人側に利息相当額の課税が発生
- 医療法上禁止されている配当類似行為とみなされるリスクもある(早期返済するように行政指導を受けることもあるようです)
- 将来、退職金で相殺するなど、複雑な調整が必要
といった問題があり、“実質的に「退職金の前借り」のような扱い”になります。
医療法人になるべくお金を残した方が税メリットは大きくなりますが、理事長個人の家計とのバランスを検討することが不可欠なのです。
まとめ ~医療法人化は“全体設計”がカギ~
医療法人化には、
- 所得分散による節税
- 事業承継のしやすさ
- 法人格による社会的信頼の向上
といった多くのメリットがあります。
しかしその一方で、
- 社会保険料の強制加入によるコスト増
- 残余財産は国庫帰属のため、出口戦略が重要
- 借入がある場合、理事長個人の資金繰り悪化
- 個人の生活費と医療法人に留保するお金のバランス
といったリスクも確実に存在します。
医療法人化を「目的」ではなく「手段」として捉え、
タイミング・収益水準・個人生活の設計・出口戦略を総合的に検討することが、
損をしない法人化の第一歩です。
おわりに:専門家の視点で「損しない設計」を
医療法人化は、制度を正しく理解し、冷静にシミュレーションすることで初めて成功するものです。
数字だけでなく、生活や将来の承継、解散までを見据えた「長期的視点」が欠かせません。
当事務所では、秋田・青森を中心に数多くの医療法人設立・経営支援を行ってきた経験から、“損しない医療法人化”のための個別診断・報酬設計・税務戦略をご提案しています。
気になることがあれば、ぜひともお気軽にご相談ください。
→ [無料相談フォームはこちら](※オンライン相談も可能)
→ お電話からのご予約も承っております

税理士の桜井晃規(さくらいあきのり)と申します。
静岡県富士宮市出身で、幼い頃から富士山を間近に過ごしてきました。
秋田県は、妻に出会うまで縁もゆかりもない土地でしたが、今では移住して本当に良かったと思っております。
現在、妻と共に、家業の税理士事務所の経営に携わっております。