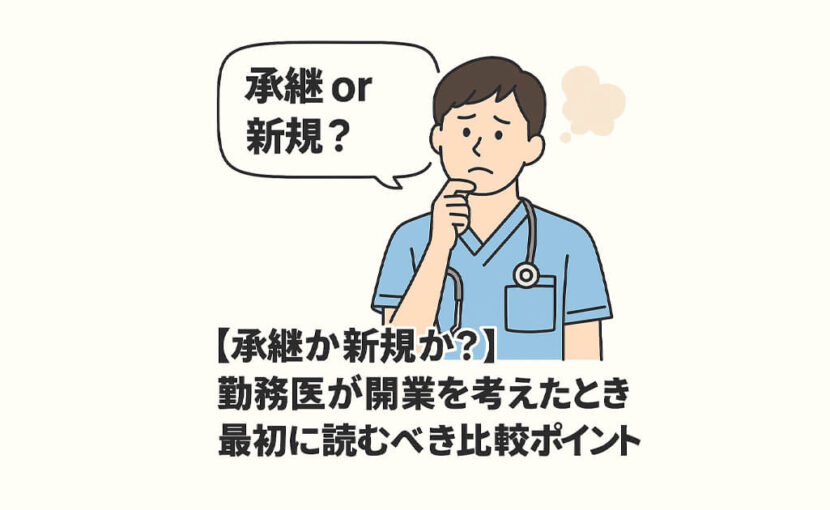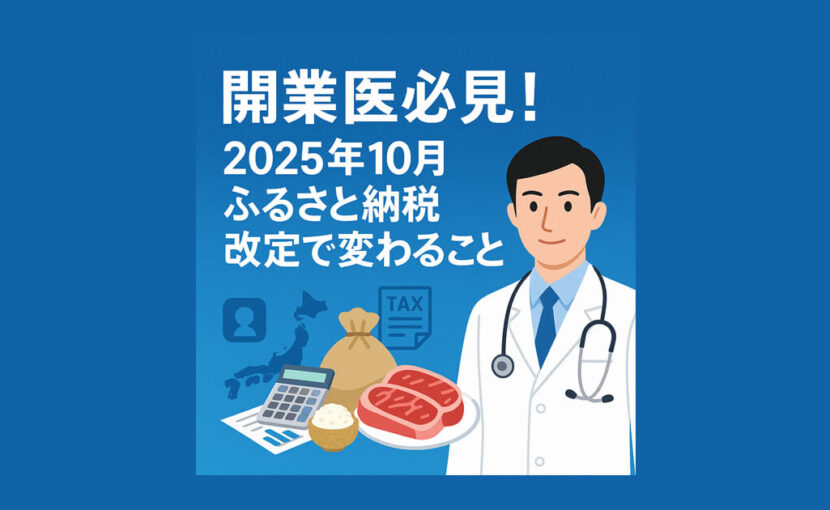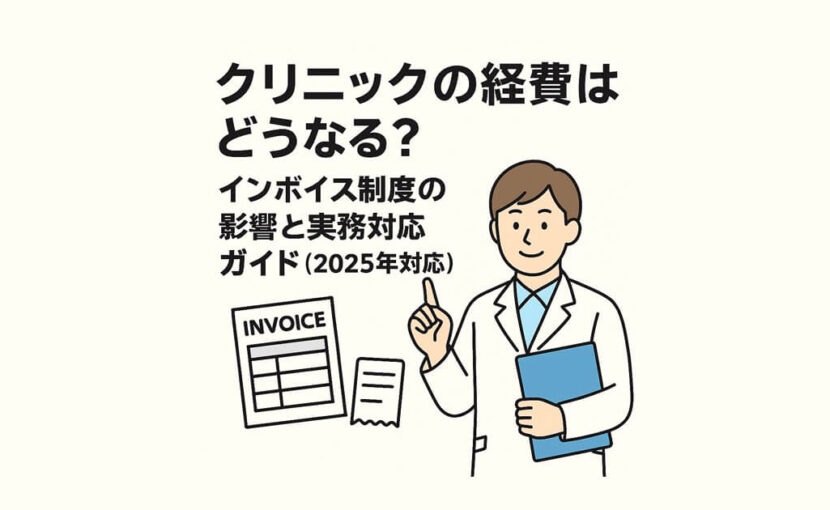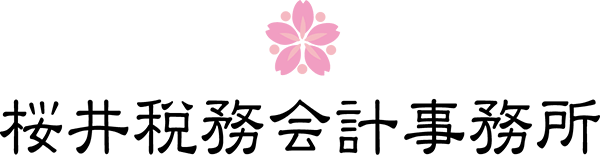こんにちは、税理士の桜井晃規です。ご覧いただきありがとうございます。
開業医の皆さまにとって、相続対策は家族の将来を守る重要な課題です。
特に、子や孫の教育費――医学部進学や留学など――は高額になりやすく、その準備と相続税対策を兼ねる方法が求められます。
「教育資金の一括贈与」制度は、非課税でまとまった金額を教育費として前渡しでき、贈与の時点で相続財産から切り離せる可能性があるという、資産承継に非常に適した制度です。
本記事では、制度の仕組み、最新の改正内容、メリット・リスクを開業医視点でわかりやすく整理して解説します。
1. 教育資金の贈与は「都度払い」でも原則非課税
親や祖父母が教育費――学費や塾代など――をその都度支払う場合、贈与税はかかりません(扶養義務の範囲内として非課税)。
ただし、この方法では教育費の支払いをする時点まで、贈与者の財産として残り続けるため、相続が発生するまでに支払いが完了していないと、結果的に相続財産として課税対象に含まれることになります。
2. 一括贈与制度とは?――相続財産からの切り離しが可能
教育資金の一括贈与制度では、金融機関(銀行や信託銀行など)を通じて、子や孫の教育資金として最大1,500万円(学校等以外は500万円まで)を一度に非課税で贈与することができます。
この制度の大きなメリットは、「将来の教育資金を前渡しし、贈与時点で相続財産から切り離せる」点にあります。
たとえば、今8歳の孫がいて自分は65歳という場合――
大学進学の時期(10年後)にどのような状況になっているかは分かりません。
都度払いでは「教育費がかかる頃に自分が生きているとは限らない」一方で、一括贈与であれば、生前に確実に孫のための資金を移しておけるのです。
3. 都度払いとの違いを整理(比較表)
| 項目 | 都度払い(非課税) | 一括贈与制度 |
| 贈与税 | 非課税 | 上限内なら非課税(受贈者の前年所得1,000万円超は対象外) |
| 相続財産から切り離せるか | 実際の教育費が発生して支払うまで残る | 贈与時に相続財産から除外できる(※23歳未満等であれば持戻しなし) |
| 手続き | 特になし | 金融機関での契約手続きが必要 |
| 未使用残額 | 該当なし | 贈与者死亡時に受贈者が23歳以上でかつ学生等でない場合は相続財産に含まれる。 ※贈与者の課税価格が5億円超の場合は23歳未満でも持戻し対象。 |
4. 開業医にとってのメリット
- 相続財産の圧縮に効果的:高額資産を持つ開業医家庭では特に有効。
- 教育費の確保:医学部や留学など高額教育費に対応しやすい。
- 生前に確実な資金移転:将来の教育費を前渡しでき、相続前に意志を実現できる。
- 税務的な明確性:金融機関経由での管理により、贈与記録や支出内容が明確化できる。
5. 注意点・リスク
- 教育以外の用途には使えないため、「生活費や娯楽には流用できない」。
- 金融機関での管理手続きや報告が必要で、手数料が発生する場合がある。
- 贈与者が死亡し、受贈者が23歳以上かつ学生等でない場合は未使用残高が相続財産に含まれる。
- 贈与者の相続税課税価格が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満であっても未使用残額が相続財産に持ち戻される。
- 受贈者の前年合計所得金額が1,000万円を超える場合、非課税措置の対象外。
- 制度の適用期限は令和8年(2026年)3月31日までであり、税制改正によって廃止・縮小される可能性もあるため、今が活用のチャンス。
6. 実践マニュアル:開業医向けステップ
- 財産目録を作成し、保有資産・負債・名義状況を明確にする。
- 相続税シミュレーション(一次相続・二次相続を含む)を実施し、将来の相続税額を把握する。
- その上で、教育資金の一括贈与を行うことでどの程度の相続税軽減が見込めるかを具体的に試算。
- 税理士と連携して贈与時期・金額・受贈者の選定を計画し、贈与漏れや過剰贈与を回避。
現状把握の上、対策を進めることを強くお勧めします。
まとめ
「教育資金の一括贈与」は、将来の教育費を生前に前渡しし、相続財産から安全に切り離すことができる制度です。
特に、高額教育費がかかる医師家庭では、教育支援と相続対策を両立できる実践的な手段となります。
ただし、5億円超の高資産層は持ち戻しリスクがある点、受贈者の所得制限(1,000万円超)、そして制度が令和8年3月31日で終了予定である点には十分注意が必要です。
制度が続いている今こそが、最も効果的な活用のタイミングです。
財産全体を俯瞰し、相続税の試算を行ったうえで、早めに税理士へ相談し、ご家族に合った贈与計画を立てましょう。
申請のサポートや実務対応で不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
→ [無料相談フォームはこちら](※オンライン相談も可能)
→ お電話からのご予約も承っております

税理士の桜井晃規(さくらいあきのり)と申します。
静岡県富士宮市出身で、幼い頃から富士山を間近に過ごしてきました。
秋田県は、妻に出会うまで縁もゆかりもない土地でしたが、今では移住して本当に良かったと思っております。
現在、妻と共に、家業の税理士事務所の経営に携わっております。